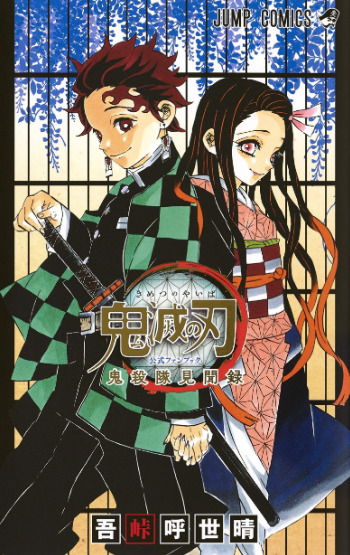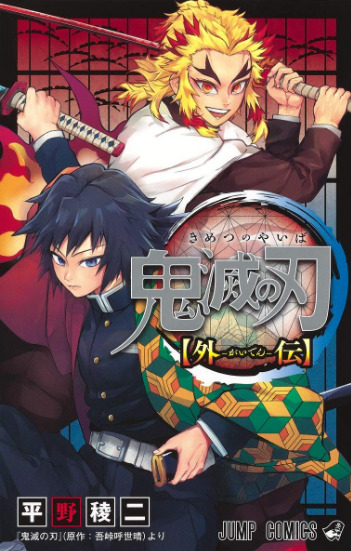作中では鬼に引け取らない力を発揮するには「痣」の発現が重要視されています。
痣を発現すると鬼に匹敵する力を得る事が出来ますが、この「痣」を発現させる事が難しく、歴代でも継国縁壱に呼吸を教わった剣士が痣を発現させていたと手記に残っている程度でした。
そこで今回は、
- 痣とは?
- 痣の出現条件は?
- 痣が出るとどうなる?
- 痣が出た柱一覧
- 痣が出なかった柱一覧
など、痣について紹介したいと思います。
痣とは
痣とは、戦国の時代に生きた始まりの呼吸の剣士・継国縁壱を筆頭に当時の剣士達が発現させた鬼の紋様に似た痣の事を指します。
過去には痣が発現しない為に思い詰めてしまう剣士が居たり、鬼殺隊がこれまでにも何度か壊滅させられかけた過程で継承が途切れたと産屋敷あまねは推測していますが、恐らく公式ファンブックで語られた様に継国巌勝が鬼となった後に鬼舞辻無惨と日の呼吸の型を知る剣士を殺害しつくしたせいで痣についての伝承が曖昧になったのでしょう。
痣の出現条件は?
痣を発現させるには二つの条件が重なる必要があります。
- 心拍数は200以上
- 体温は39度以上
以上の様に、刀鍛冶の里編で時透無一郎が痣を発現させた際の己の体調と治療中に体温計で計った体温を元に基準を示しており、そこで死ぬか死なないかで痣が出る者と出ない者が篩に掛けられると述べました。
また、痣の者が一人現れると共鳴するように周りの者たちにも痣が現れると始まりの呼吸の剣士の一人の手記に残されており、今代で痣を一番に発現させたのは竈門炭治郎です。
痣を出るとどうなるの?
継国縁壱と同じような痣が発現した者は格段に力が向上すると公式ファンブックで書かれており、実際の戦闘描写を見ても概ねその通りの印象です。
メリットとしては、
というもので、痣を発現させた者は何れも身体能力や戦闘能力が格段に上がっており、そこから「透き通る世界」や「赫刀」の領域に達する柱も出ています。
痣を発現させる事が始まりの呼吸・継国縁壱の強さに近づく第一段階なのかもしれません。
また、胡蝶しのぶの発言では傷の治りも異常に早くなるそうです。
痣を発現させるデメリットは?
痣を発現させると力の向上が見込めますが、一方でデメリットも存在します。
それは、痣を発現させた者は例外なく25歳を迎える前に死ぬと言われており、当時継国縁壱が生きた時代の剣士達も痣を発現させていましたが例外なく25歳を迎える前に死に絶えました。
黒死牟曰く痣の出現は寿命の前借りに過ぎないそうです。
痣が出ても死なない例外が存在する
痣者は例外なく25歳を迎える前に死ぬのは確かですが、唯一一人だけ痣が出ても死なない者が居ました。
それは始まりの呼吸の剣士・継国縁壱であり、縁壱は痣が発現しても齢八十を超えるまで生きており、寿命を迎える寸前まで全盛期の肉体や剣技を維持し続けた特別な肉体を持っていましたが、恐らく日の呼吸に適応する唯一の人間だったからです。
本人が鬼舞辻無惨を倒す為に特別強く造られて生まれてきたと発言している通り、歴史上でも縁壱以外の痣者は痣に適応出来ずに死んでいきました。
また、竈門炭十郎も生まれた時から薄い痣模様があったそうですが、炭十郎は日の呼吸の型「ヒノカミ神楽」を会得していたり「透き通る世界」に達しているので、病死となっていますが痣との関係もありそうですね。
最初に痣を発現させたのは竈門炭治郎
最初に痣を発現させたのは竈門炭治郎ですが、その描写が収録されているのは単行本11巻第94話「何とかして」です。(アニメ遊郭編第11話「絶対諦めない」)
上弦の陸・堕姫と妓夫太郎戦の最中、妓夫太郎の頸を斬り落とす直前、炭治郎は渾身の一撃では足りないとしてその百倍の力を捻り出そうとした所、痣の紋様が色濃く変化し発現に至りました。
それによって、これまで硬くて斬れなかった上弦の頸も痣の発現により斬り落とす事が出来ます。
痣が出現した柱と出なかった柱の一覧
◇痣を発現させた柱
| 【名前】 | 【痣の紋様と巻数・話数】 | |
| 霞柱 | 時透無一郎 |
|
| 恋柱 | 甘露寺蜜璃 |
|
| 水柱 | 富岡義勇 |
|
| 岩柱 | 悲鳴嶼行冥 |
|
| 風柱 | 不死川実弥 |
|
| 蛇柱 | 伊黒小芭内 |
|
◇痣が発現しなかった柱
| 【名前】 | |
| 炎柱 | 煉獄杏寿郎 |
| 音柱 | 宇随天元 |
| 蟲柱 | 胡蝶しのぶ |
時透無一郎の痣出現シーン
無一郎が痣を発現させたのは単行本14巻第118話です。
刀鍛冶の里編、上弦の伍・玉壺との戦いの際に自分を守る為に負傷した小鉄や炭治郎に言われた言葉から失っていた記憶を取り戻すと、怒りから感情が抑えきれなくなり痣が発現しました。
これにより玉壺を一騎打ちで討伐する程の力の向上を遂げると、上弦の壱・黒死牟との戦いでは透き通る世界や赫刀まで発現するなど、最速の進化を見せています。
甘露寺蜜璃の痣出現シーン
甘露寺蜜璃が痣を発現させたのは単行本14巻第124話です。
刀鍛冶の里編、上弦の肆・半天狗の分裂体である憎珀天との戦いの最中、自分を認めてくれた鬼殺隊や命懸けで守ってくれる炭治郎達を守る為に本気になった途端に痣が発現しました。
不死身の憎珀天相手に夜明けまで一人で足止めし続ける事で半天狗の本体を炭治郎達が打ち取る時間稼ぎをする他、鬼舞辻無惨との戦いでは素手で無惨の腕をもぎ取る怪力を見せています。
富岡義勇の痣出現シーン
富岡義勇の痣が発現したのは単行本17巻第150話です。
無限城、上弦の参・猗窩座との戦いの最中、己が圧倒される強者と出会い短時間で感覚が鋭く錬磨されると、閉じていた感覚が叩き起こされ実力を引き出すように痣が発現しました。
これにより猗窩座との戦いに順応し炭治郎と共に撃破すると、無惨戦では不死川実弥との連携で赫刀を発現します。
悲鳴嶼行冥の痣出現シーン
悲鳴嶼行冥の痣が発現したのは単行本19巻第169話です。
無限城、上弦の壱・黒死牟との戦いの最中、相手が相手なので出し惜しみ無く自らの意志で痣を発現させています。
悲鳴嶼の場合は柱合会議で痣の発現条件を聞いた後、全体稽古や柱稽古の修行の最中に身に付けたものでしょう。
不死川実弥の痣出現シーン
不死川実弥の痣が発現したのは単行本20巻第170話です。
無限城、上弦の壱・黒死牟との戦いの最中、黒死牟にやられた傷を縫い合わせて仕切り直しする際、深呼吸と共に痣が発現しています。
悲鳴嶼とのコンビネーションで黒死牟を追い詰めると悲鳴嶼と刀を打ち合う事で赫刀を発現しており、無惨戦では富岡義勇と連携し赫刀を発現させました。
伊黒小芭内の痣出現シーン
伊黒小芭内の痣が発現したのは単行本22巻第189話です。
市街地戦、鬼舞辻無惨との総力戦の最中、伊黒は無惨の毒を受けた状態で誰よりも戦果を上げていない事から有効な攻撃を与える方法を模索しており、過去の経験から非力な手でも簪一本で分厚い格子を破る事が出来た事、時透無一郎が死ぬ間際に刀の色に関わらず刃を赫く染めた事を分析し、刀を強く握りしめる事で強い衝撃を受けた刀の温度が上がったと推察しました。
そして、命の危機に瀕した時、万力の握力で赫刀を発現させるとほぼ同時に痣が発現しています。
過去に痣が発現していた剣士
継国縁壱は生まれながらにして痣を発現させており、鬼殺隊となった縁壱に呼吸を教わる事で当時の鬼殺隊や継国巌勝(黒死牟)も痣を発現する事が出来ました。
しかし、日の呼吸の適性ではない剣士達は例外なく25歳を迎える前に死亡しており、巌勝は鬼になる事で寿命を回避しています。
痣や痣が発現した柱のまとめ
- 痣とは、寿命を前借りする事で得られる力の向上
- 痣を発現したものは25歳を迎える前に亡くなる
- 死亡していない例外は日の呼吸の適性がある継国縁壱のみ
- 今世で一番に痣を発現させたのは竈門炭治郎
- 痣を発現させた柱は順に、時透無一郎、甘露寺蜜璃、富岡義勇、悲鳴嶼行冥、不死川実弥、伊黒小芭内の6名
- 痣が出なかったのは、煉獄杏寿郎、宇随天元、胡蝶しのぶの3名
今回は痣について、痣が発現した時のメリットやどのタイミングで誰が痣を発現させたか、また痣のデメリットについて紹介いたしました。
痣については黒死牟や無惨のせいで伝承に曖昧な部分が生じてしまいましたが、ストーリーが進むにつれて少しずつ分かってきた要素もあり、柱稽古や上弦の鬼、そして無惨と戦う最中に発現させた柱も居ます。
寿命の前借りに過ぎないので痣を発現させた柱で最後まで生き残った者は恐らく25歳を迎える前に死亡している可能性があるので、無惨を倒したのに少し物悲しいですね。